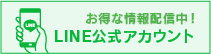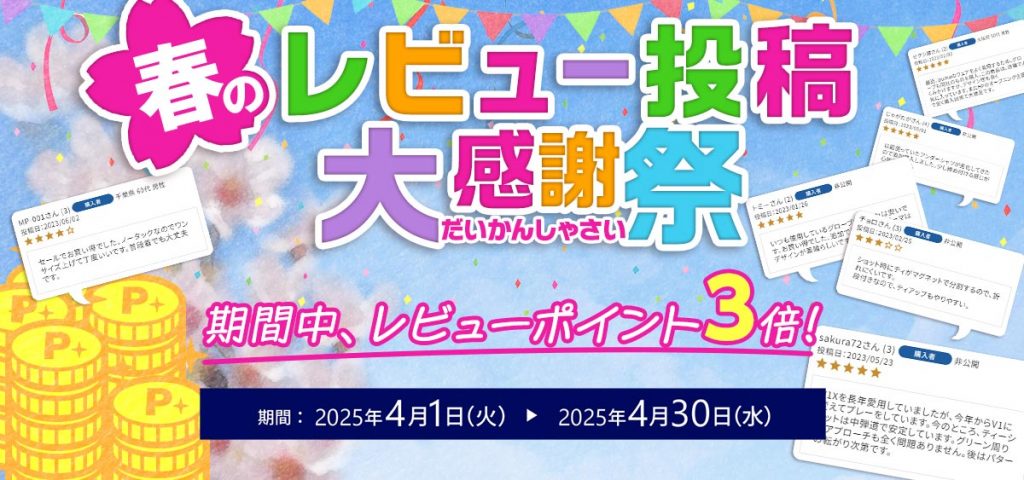ウェッジがうまく打てません・・・
練習場だとうまく打てるのにコースでは球が上がらない…
ボールの手前を打ってしまう…
あとちょっとでグリーンにのるというところで手痛いミス…思い出すだけで嫌な気持ちになりますよね。
もしかしたらそのウェッジのミス、アイアン~ウェッジの重さが影響しているかもしれません。

ウェッジとは?

アプローチで使うクラブの「ウェッジ」。そもそも「ウェッジ」とは何でしょうか?
「ウェッジ」とはアイアンと言われるクラブの仲間で長さが短く、ロフト角が40°~60°くらいのクラブの総称のことです。
アイアン番手を数字で表す場合が多いのですが9番アイアン以下(※1)の番手でPW(ピッチングウェッジ)、AW(アプローチウェッジ)、SW(サンドウェッジ)(※2)などの代表的な呼び名があります。
アイアンの中では「距離を飛ばす」というより「距離を調整して打つ」ことに使う場合が多いクラブになります。
※1 モデルによっては10番、11番以下の場合があります。
※2 モデルによってはGW(ギャップウェッジ)、UW(ユーティリティー)、DW(デュアルウェッジ)、AS(アプローチ/サンド)などあります。
ウェッジを選ぶ前に…「使っているクラブ」と「自分のこと」知っていますか?
新しいクラブを選ぶ時「ミスを減らしたい」「こういうショットが打ちたい」「今の自分に合うクラブが欲しい」など 目的や希望を持ってクラブを探すと思いますがその出発点が「今、使っているクラブ」と「自分のこと」を知るところです。
今、使っているクラブのシャフトの種類は?
アイアンセットは・・・?
スチールのアイアンセット

カーボンシャフトのアイアンセット

ウェッジは・・・?
スチールシャフトのウェッジ

カーボンシャフトのウェッジ

今、ウェッジでのミスの傾向は?
❶打点が安定してなく色々なミスがでてしまう

❷ボールの上を打ってしまうミスが多い(トップしてしまう)

❸ボールの手前の地面を打ってしまうミスが多い(ダフってしまう)

シャフトの種類と重さを基準にウェッジを選ぶには?
シャフトの重さの違いでクラブの打ちやすさ・安定感は変わってきます。
「スチールシャフト」・「カーボンシャフト」の重さの違い
一般的なカーボンシャフトの重量 約40g~60g
一般的なスチールシャフトの重量 約90g~120g
その差は最大80g!
もし今お使いのセットでアイアンとウェッジでシャフトの種類やタイプが違う場合、この重さの違いが思わぬミスの要因になっているかもしれません。
シャフトはできるだけ近い重さで揃えることをおすすめします。
アイアンとウェッジのシャフトの組み合わせパターン
パターンA
スチールシャフトのアイアンセット

スチールシャフトのウェッジ

同じスチール同士でも重さの違いに注意
パターンB
スチールシャフトのアイアンセット

カーボンシャフトのウェッジ

アイアンを打った後、ウェッジを持った時に軽く感じる場合あり
パターンC
カーボンシャフトのアイアンセット

カーボンシャフトのウェッジ

同じカーボン同士でも重さの違いに注意
パターンD
カーボンシャフトのアイアンセット

スチールシャフトのウェッジ

アイアンを打った後、ウェッジを持った時に重たく感じる場合あり
ミスの傾向で選ぶなら
❶打点が安定してなく色々なミスがでてしまう

アイアンの全体的な重量が整っていない可能性あり
パターンA(スチールシャフトのアイアンセット、スチールシャフトのウェッジ)またはパターンC(カーボンシャフトのアイアンセット、カーボンシャフトのウェッジ)でシャフトの重さを近いモデルにして流れを合わせてみる。
❷ボールの上を打ってしまうミスが多い(トップしてしまう)

クラブヘッドがボールに届いていない
パターンA(スチールシャフトのアイアンセット、スチールシャフトのウェッジ)またはパターンD(カーボンシャフトのアイアンセット、スチールシャフトのウェッジ)、またはアイアン全体の重量がある組み合わせがおすすめ。
❸ボールの手前の地面を打ってしまうミスが多い(ダフってしまう)

クラブの重さが極端に重い場合と前に打った時にトップしてしまい、スイングの調整がうまくできずにボールの手前を打ってしまっている場合があります。
極端にウェッジが重い場合以外は軽くせずパターンA(スチールシャフトのアイアンセット、スチールシャフトのウェッジ)またはパターンC(カーボンシャフトのアイアンセット、カーボンシャフトのウェッジ)のようにシャフトの重さを近いモデルにして流れを合わせてみるのがおすすめ。
終わりに
ゴルフでは複数のクラブを使い分けてコースを攻略するスポーツなので「一回前に打ったクラブの感覚」から大きな影響を受ける場合があります。
「前に振ったものの感覚」と「今から振るクラブの感覚」の差が少ない方が安定した打点で捉えられ、ミスを軽減できるといったことをイメージしてもらえればと思います。